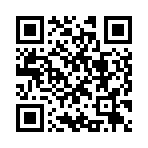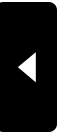2010年08月16日
甲斐駒ケ岳、黒戸尾根を登りました、2010年8月13日(3)
今日は、とても暑かったですね、、。
甲府で、37度、、、。
仕事の能率が落ちました。
さて、8月13日、厳しい厳しい、黒戸尾根から甲斐駒ケ岳に登りました。
登りで、6時間半を費やして、山頂に立ちました。
(1)はこちらです。
(2)はこちらです。
それまでに既に3時間弱を費やして、登ってきました
屏風小屋跡を9:05には出発です。
水分はしっかりとっています。
スポーツドリンク。
ほとんど凍らせて持参しますから、冷たく飲めます。
9:46に七丈小屋に到着するまでは、厳しい梯子、鎖が
連続する区間で、垂直の梯子、それに続く鎖、、。
その辺りが転落の恐怖を感じるところでしょうか、、。
しかし、つかまって慎重に行けば、そしてバランスを崩さなければ、
落ちない、、そう言い聞かせます。
途中で、女性2名のトレラン走者に追い越され、厳しい垂直の鎖場の
ところで、休んでいた2名を追い抜きました。


続きを読む
甲府で、37度、、、。
仕事の能率が落ちました。
さて、8月13日、厳しい厳しい、黒戸尾根から甲斐駒ケ岳に登りました。
登りで、6時間半を費やして、山頂に立ちました。
(1)はこちらです。
(2)はこちらです。
それまでに既に3時間弱を費やして、登ってきました
屏風小屋跡を9:05には出発です。
水分はしっかりとっています。
スポーツドリンク。
ほとんど凍らせて持参しますから、冷たく飲めます。
9:46に七丈小屋に到着するまでは、厳しい梯子、鎖が
連続する区間で、垂直の梯子、それに続く鎖、、。
その辺りが転落の恐怖を感じるところでしょうか、、。
しかし、つかまって慎重に行けば、そしてバランスを崩さなければ、
落ちない、、そう言い聞かせます。
途中で、女性2名のトレラン走者に追い越され、厳しい垂直の鎖場の
ところで、休んでいた2名を追い抜きました。
続きを読む
2010年08月15日
甲斐駒ケ岳、黒戸尾根を登りました、2010年8月13日(2)
8月13日、厳しい厳しい、黒戸尾根から甲斐駒ケ岳に登りました。
トレランが多く、山頂直下ではライチョウ発見。
登りで、6時間半を費やして、山頂に立ちました。
(1)はこちらです。
さて、5:00には尾白川渓谷駐車場に到着しました。
国道20号線を道の駅はくしゅうのところで山のほうに向います。
親水公園何という看板を目印に、、。
さて、トイレも行って、支度をします。
トレランの人が多く、なんと軽装であること、、
驚きますね
どうせ追い越されますから、先に行ってもらったほうが良いです。
そして、トレランの人が出発してから、ようやくこちらも出発です。
5:15には、出発。
まずは、竹宇駒ケ岳神社。
それかつり橋。
神社は火災で焼失して近年作り変えられました。


気を引き締める看板

薄暗い樹林帯をひたすら登ります。
とにかく暗く、下山時もかなり暗く、陰気な感じ。
そこかしこにキノコが繁茂しています。
続きを読む
トレランが多く、山頂直下ではライチョウ発見。
登りで、6時間半を費やして、山頂に立ちました。
(1)はこちらです。
さて、5:00には尾白川渓谷駐車場に到着しました。
国道20号線を道の駅はくしゅうのところで山のほうに向います。
親水公園何という看板を目印に、、。
さて、トイレも行って、支度をします。
トレランの人が多く、なんと軽装であること、、
驚きますね
どうせ追い越されますから、先に行ってもらったほうが良いです。
そして、トレランの人が出発してから、ようやくこちらも出発です。
5:15には、出発。
まずは、竹宇駒ケ岳神社。
それかつり橋。
神社は火災で焼失して近年作り変えられました。
気を引き締める看板
薄暗い樹林帯をひたすら登ります。
とにかく暗く、下山時もかなり暗く、陰気な感じ。
そこかしこにキノコが繁茂しています。
続きを読む
2010年08月14日
甲斐駒ケ岳、黒戸尾根を登りました、2010年8月13日(1)
木曜日、金曜日は、東京ですが、今週は休み。
台風の直接的影響はなかった山梨ですが、
晴天を期待し、ようやく甲斐駒ケ岳へ。
バス等の時間を気にしたくないし、
3年ぶり、3回目となる黒戸尾根に挑戦。
もちろん登り始めは、尾白川渓谷駐車場。
さて、このルートは最近、めっきり
メジャーになったのか、多くの記録が見られます。
本人的には、とても簡単そうに登っているような記録も多く、
他の人が、安易に飛びつくリスクを感じます。
トレランの人がトレーニングに使っているようで、
一般的な登山者の時間記録とは、かけ離れており、
それをそのまま鵜呑みにすると大変な目に遭うでしょう。
こんなルートです。
こんな時間で登りました。
尾白川渓谷駐車場5:15-6:45笹の平分岐6:47-7:54刃渡り手前8:04
-8:22刀利天狗8:25-9:02屏風小屋跡9:05-9:46七丈小屋9:50-
10:45八合目ご来光場10:50-11:45甲斐駒ケ岳山頂12:06-
13:21七丈小屋13:34-14:12屏風小屋跡14:15-14:45刀利天狗14:48-
15:02刃渡り後15:10-16:55尾白川渓谷駐車場
総合時間11時間40分、歩行時間:10時間25分

続きを読む
台風の直接的影響はなかった山梨ですが、
晴天を期待し、ようやく甲斐駒ケ岳へ。
バス等の時間を気にしたくないし、
3年ぶり、3回目となる黒戸尾根に挑戦。
もちろん登り始めは、尾白川渓谷駐車場。
さて、このルートは最近、めっきり
メジャーになったのか、多くの記録が見られます。
本人的には、とても簡単そうに登っているような記録も多く、
他の人が、安易に飛びつくリスクを感じます。
トレランの人がトレーニングに使っているようで、
一般的な登山者の時間記録とは、かけ離れており、
それをそのまま鵜呑みにすると大変な目に遭うでしょう。
こんなルートです。
こんな時間で登りました。
尾白川渓谷駐車場5:15-6:45笹の平分岐6:47-7:54刃渡り手前8:04
-8:22刀利天狗8:25-9:02屏風小屋跡9:05-9:46七丈小屋9:50-
10:45八合目ご来光場10:50-11:45甲斐駒ケ岳山頂12:06-
13:21七丈小屋13:34-14:12屏風小屋跡14:15-14:45刀利天狗14:48-
15:02刃渡り後15:10-16:55尾白川渓谷駐車場
総合時間11時間40分、歩行時間:10時間25分
続きを読む
2009年09月16日
北沢峠から甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、09年9月9、10日(4)
(1)直登分岐までのお話はこちらです。
(2)仙水小屋までのお話はこちらです。
(3)仙水小屋のお話などはこちらです。
ちょっと繰り返しにもなりますが、、、
宿泊した仙水小屋では、3:30に朝食。
当初、北沢峠からのバスは、12:55を予定していたものの、これなら
11:05でも間に合うと思うようになったのでした。
(11:05のバスは、土日、休日はありません。)
とても早い朝食です。
4:15仙水小屋を出発しましたが、当然真っ暗で、ヘッドライトを
点灯させて、北沢駒仙小屋を目指します。
なんどか「あれ、、」と思う場面もありましたが、何とか、北沢駒仙小屋に
到着。テントは10張りくらいでした。
やはり、夜間の歩行は怖いです。
そこから仙丈ケ岳への登山道の2合目に
合流する近道から2合目を目指します。
この道では、夜明けを迎える北岳が見えたり、
思わぬところから富士が見えるの
ですが、樹林が邪魔します。
明るさも増し、ヘッドライトは消灯しました。
5:32二合目合流点
ご夫婦が北沢峠から登って来られました
5:35二合目合流点発
2合目に合流して、しばらくは、普通の登山道。
時折、大きな段差が現われます。
まだ樹林帯の歩きです。
だんだん明るくなります。
北岳のシルエット

続きを読む
(2)仙水小屋までのお話はこちらです。
(3)仙水小屋のお話などはこちらです。
ちょっと繰り返しにもなりますが、、、
宿泊した仙水小屋では、3:30に朝食。
当初、北沢峠からのバスは、12:55を予定していたものの、これなら
11:05でも間に合うと思うようになったのでした。
(11:05のバスは、土日、休日はありません。)
とても早い朝食です。
4:15仙水小屋を出発しましたが、当然真っ暗で、ヘッドライトを
点灯させて、北沢駒仙小屋を目指します。
なんどか「あれ、、」と思う場面もありましたが、何とか、北沢駒仙小屋に
到着。テントは10張りくらいでした。
やはり、夜間の歩行は怖いです。
そこから仙丈ケ岳への登山道の2合目に
合流する近道から2合目を目指します。
この道では、夜明けを迎える北岳が見えたり、
思わぬところから富士が見えるの
ですが、樹林が邪魔します。
明るさも増し、ヘッドライトは消灯しました。
5:32二合目合流点
ご夫婦が北沢峠から登って来られました
5:35二合目合流点発
2合目に合流して、しばらくは、普通の登山道。
時折、大きな段差が現われます。
まだ樹林帯の歩きです。
だんだん明るくなります。
北岳のシルエット
続きを読む
2009年09月14日
北沢峠から甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、09年9月9、10日(3)
(1)直登分岐までのお話はこちらです。
(2)仙水小屋までのお話はこちらです。
仙水小屋には、もうたくさんの人が到着していました。
大抵の方は、北沢峠から歩いてきて翌日甲斐駒ケ岳に登られるようです。
私も2005年はそうでした。
小屋に着いたら、着替えて、リュックの整理をして、、、
ようやく落ち着きます。
予約したのは前日でしたが、聞いてみた他の方も
前日に予約された方がたくさんいました。
定員30名。
それ以上は取らない。
そういう方針です。
夕食は、16:30からという説明を予約時に受けておりましたが、
結局、それより少し早い時間に夕食となりました。
ちょっと冷えるのですが、外で頂きます。

続きを読む
(2)仙水小屋までのお話はこちらです。
仙水小屋には、もうたくさんの人が到着していました。
大抵の方は、北沢峠から歩いてきて翌日甲斐駒ケ岳に登られるようです。
私も2005年はそうでした。
小屋に着いたら、着替えて、リュックの整理をして、、、
ようやく落ち着きます。
予約したのは前日でしたが、聞いてみた他の方も
前日に予約された方がたくさんいました。
定員30名。
それ以上は取らない。
そういう方針です。
夕食は、16:30からという説明を予約時に受けておりましたが、
結局、それより少し早い時間に夕食となりました。
ちょっと冷えるのですが、外で頂きます。
続きを読む
2009年09月12日
北沢峠から甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、09年9月9、10日(2)
2009年09月11日
北沢峠から甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、09年9月9、10日(1)
9月9日、10日で北沢峠を基点に甲斐駒ケ岳と仙丈ケ岳を登りました。
仙丈ケ岳は、2005年以降登っておらず、且つ、甲斐駒ケ岳も2006年、
2007年は黒戸尾根から死ぬ思いで日帰りしたものの、昨年は、登らず、
それなら2つの山を同時に登れるのは、北沢峠からということになり、実行。
宿泊も2005年に最後に仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳を登ったときに泊まった
仙水小屋に泊まることに決めていました。
ピークも過ぎて、閑散の北沢峠、こういうのがいいです。
 続きを読む
続きを読む
仙丈ケ岳は、2005年以降登っておらず、且つ、甲斐駒ケ岳も2006年、
2007年は黒戸尾根から死ぬ思いで日帰りしたものの、昨年は、登らず、
それなら2つの山を同時に登れるのは、北沢峠からということになり、実行。
宿泊も2005年に最後に仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳を登ったときに泊まった
仙水小屋に泊まることに決めていました。
ピークも過ぎて、閑散の北沢峠、こういうのがいいです。
2009年09月10日
甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、仙水小屋の宿泊、09年9,10日
仙丈ケ岳は2005年以来、
甲斐駒ケ岳は2007年以来となりました。
鳳凰三山、北岳と比べると回数が少ないですね。
北沢峠とい難物が嫌なのでしょう。
今回もちょっと22名の団体がいただけで、それほどの混雑では
なかったのですが、嫌でした。
困りますね。
広河原の北沢峠行きバス停
 続きを読む
続きを読む
甲斐駒ケ岳は2007年以来となりました。
鳳凰三山、北岳と比べると回数が少ないですね。
北沢峠とい難物が嫌なのでしょう。
今回もちょっと22名の団体がいただけで、それほどの混雑では
なかったのですが、嫌でした。
困りますね。
広河原の北沢峠行きバス停
2008年05月26日
仙水小屋、食事が良かった甲斐駒、仙丈 05年8月10、11日
この年の8月3日、4日には、山梨の誇り
白峰三山、北岳、間ノ岳、農鳥岳を縦走している。その1週間後の10、11日
今度は、仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳に登頂している。
ところが、仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳の山行記録がない。
今からは考えられない。
幸いなことに写真は残していた。
記憶を辿る。
2005年8月10、11日
山=仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳
続きを読む
白峰三山、北岳、間ノ岳、農鳥岳を縦走している。その1週間後の10、11日
今度は、仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳に登頂している。
ところが、仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳の山行記録がない。
今からは考えられない。
幸いなことに写真は残していた。
記憶を辿る。
2005年8月10、11日
山=仙丈ケ岳、甲斐駒ケ岳
続きを読む
2008年04月01日
甲斐駒ケ岳黒戸尾根日帰り、(06年10月20日)
昨年から計画。どうしても日帰りしたいところ。
危ない場合は、七丈小屋での宿泊も考えた。
日没が早いため、早く行動する必要。ただ、当日は、4:17に起きて自宅出発は、5:00。
登山開始は、5:50になってしまった。
続きを読む
危ない場合は、七丈小屋での宿泊も考えた。
日没が早いため、早く行動する必要。ただ、当日は、4:17に起きて自宅出発は、5:00。
登山開始は、5:50になってしまった。
続きを読む
2008年04月01日
甲斐駒ケ岳黒戸尾根を日帰り、(07年10月23日)
昨年に続いて、甲斐駒黒戸尾根の日帰り。
昨年は小屋にも泊まるつもりでいたが、食事が提供されない、
「日帰り」という小屋の管理人の言葉に後押しされて、日帰りした。
今年も挑戦の意味をこめて。
続きを読む
昨年は小屋にも泊まるつもりでいたが、食事が提供されない、
「日帰り」という小屋の管理人の言葉に後押しされて、日帰りした。
今年も挑戦の意味をこめて。
続きを読む