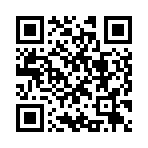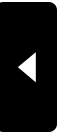2009年06月06日
1月以来の甲武信岳、西沢渓谷から、09年6月3日(2)
(1)はこちらです。
近丸新道と、歩いてきた徳ちゃん新道の合流点での、休憩が終了し、
出発しようと思ったら、近丸新道を登ってきた男性1名が、、、。
半袖Tシャツに汗がにじみ、少し冷えるのではないかと心配。
その男性、登山が初めてということでした。
初めての登山に甲武信岳を、しかも西沢渓谷から登るなって、すごいです。
でもやはり、その後疲れたのか、私がこの合流点を先行し、甲武信ヶ岳に登頂し、
木賊山から下っているときに再び会いました。
だいぶ歩みが遅くなったようでした。

近丸新道と、歩いてきた徳ちゃん新道の合流点での、休憩が終了し、
出発しようと思ったら、近丸新道を登ってきた男性1名が、、、。
半袖Tシャツに汗がにじみ、少し冷えるのではないかと心配。
その男性、登山が初めてということでした。
初めての登山に甲武信岳を、しかも西沢渓谷から登るなって、すごいです。
でもやはり、その後疲れたのか、私がこの合流点を先行し、甲武信ヶ岳に登頂し、
木賊山から下っているときに再び会いました。
だいぶ歩みが遅くなったようでした。
その際、甲武信ヶ岳のこの西沢渓谷のルートは敬遠されがちなきつい
ルートであることを話したら、「選択の失敗かな」と悔やんでいたので、
そんなことはないと励ましました。
その後、無事甲武信岳に登頂し、無事下山できたでしょうか?
近丸新道については、この登山者と、実は、先を歩いていたもう
1名の男性が通過し、その二人から、情報を得ています。
一部崩れていると、、、。
私も一度歩いていたのですが、トロッコの軌道跡があったとは思いますが、
その後は信州側や徳ちゃん新道ばかり歩いており、また、機会があったら歩きたいです。
7:30合流点発
ここから樹林帯の急登りになるまでシャクナゲトンネルです。
ちょうど見ごろなのかも知れません。
あたり一面に、それこそ山梨百名山の甘利山のツツジのように、
密集する感じではありませんが、結構いい感じで咲いていますね。
だから、何度も立ち止まって、カメラを向けるのでした。


これから向う木賊山

この辺りは登山道が狭いので、昨日甲武信小屋に泊まったグループが
結構下りてきますが、すれ違いも難しいような、、、。


これで20名の団体にでも待たされたら、、、、。
リーダー不在、、、、、と叫んでしまいそうです。
今回もそんな年配グループがいたいた。
甲武信小屋には、昨日は60名も泊まったようです。
多いです。
こんな人たちもいたでしょうか??
昨日の甲武信小屋、、、、。
狭いシャクナゲトンネルを抜ければ、急登りの樹林帯に入ります。
ひたすら高度を稼ぎます。

左には、鶏冠山、右には、破風山などが透けて見えています。
無言の急登りをこなしていても数組が下りてきます。
やはり、シャクナゲの時期で甲武信小屋も混んでいたのでしょうか?
崩れた場所に出ると一気に展望が開けます。
富士山がなんとか見えています。
曇っていますが、なんとか、眺望はありますね。
黒金山も見えるし、国師が岳も見えるし、これから登る木賊山も近くなるし、、。


でも寒いです。
急登りの樹林帯から鶏冠尾根より高くなり、風が
通るようになって、冷たい風を感じていました。
一度、暑くて脱いでいた、一枚を着ます。
それから、しばらく行くと、標高でも2400m近くなり、登山道に雪が出てきます。

一部は凍結もしており、注意します。
とはいえ、脇を歩いたり、人の歩いたところを慎重に歩いたり、
凍結している部分に不用意に乗るのを避ければ、問題なく、アイゼンは不要でしょう。
縦走路にぶつかってからも雪がありますが、アイゼン不要でしょう。

前方に登山者が見えます。
実は、この登山者がこの日、私が知っている範囲のもう1名の近丸新道を登ってきた登山者。
山頂でも会うことになります。
縦走路の雪

9:01木賊山
三等三角点があり、ベンチもあります。
1月には、雪に埋もれていた木賊山の指導標も全部露出していました。


9:06木賊山発甲武信小屋に下ります。
すぐに麓から見えにくい甲武信岳の全貌が、いい感じです。

その際、滑りやすいザレ場を通過しますので、注意しましょう。

いつも風の通り道で冷たい風が吹いていました。
ザレ場に冷たい風。
厳冬期など、緊張するところです。
ザレ場を過ぎると風も落ち着き、甲武信小屋への下りでトラバース気味に下りますが、
ちょっと、嫌な雪がありますが、慎重に行けば問題ありません。
ちょっとヒヤッとしましたが、、、、。

9:17甲武信小屋
小屋に雪がありません。

当たり前ですが、屋根に雪がのった甲武信小屋の姿が焼きついています。
先ほどから見えていた登山者が休んでいました。
先に私が休憩なしで先行し、最後の登りにかかります。
2008年2月には、この最後の登りに40分以上も費やしました。
すごい登山でした。
さて、雪がなく、だいぶ楽ではありますが、そうは言っても、つらかったです。
でも、わずか15分の登りで山頂でした。
9:32甲武信岳山頂
続く。
ルートであることを話したら、「選択の失敗かな」と悔やんでいたので、
そんなことはないと励ましました。
その後、無事甲武信岳に登頂し、無事下山できたでしょうか?
近丸新道については、この登山者と、実は、先を歩いていたもう
1名の男性が通過し、その二人から、情報を得ています。
一部崩れていると、、、。
私も一度歩いていたのですが、トロッコの軌道跡があったとは思いますが、
その後は信州側や徳ちゃん新道ばかり歩いており、また、機会があったら歩きたいです。
7:30合流点発
ここから樹林帯の急登りになるまでシャクナゲトンネルです。
ちょうど見ごろなのかも知れません。
あたり一面に、それこそ山梨百名山の甘利山のツツジのように、
密集する感じではありませんが、結構いい感じで咲いていますね。
だから、何度も立ち止まって、カメラを向けるのでした。
これから向う木賊山
この辺りは登山道が狭いので、昨日甲武信小屋に泊まったグループが
結構下りてきますが、すれ違いも難しいような、、、。
これで20名の団体にでも待たされたら、、、、。
リーダー不在、、、、、と叫んでしまいそうです。
今回もそんな年配グループがいたいた。
甲武信小屋には、昨日は60名も泊まったようです。
多いです。
こんな人たちもいたでしょうか??
昨日の甲武信小屋、、、、。
狭いシャクナゲトンネルを抜ければ、急登りの樹林帯に入ります。
ひたすら高度を稼ぎます。
左には、鶏冠山、右には、破風山などが透けて見えています。
無言の急登りをこなしていても数組が下りてきます。
やはり、シャクナゲの時期で甲武信小屋も混んでいたのでしょうか?
崩れた場所に出ると一気に展望が開けます。
富士山がなんとか見えています。
曇っていますが、なんとか、眺望はありますね。
黒金山も見えるし、国師が岳も見えるし、これから登る木賊山も近くなるし、、。
でも寒いです。
急登りの樹林帯から鶏冠尾根より高くなり、風が
通るようになって、冷たい風を感じていました。
一度、暑くて脱いでいた、一枚を着ます。
それから、しばらく行くと、標高でも2400m近くなり、登山道に雪が出てきます。
一部は凍結もしており、注意します。
とはいえ、脇を歩いたり、人の歩いたところを慎重に歩いたり、
凍結している部分に不用意に乗るのを避ければ、問題なく、アイゼンは不要でしょう。
縦走路にぶつかってからも雪がありますが、アイゼン不要でしょう。
前方に登山者が見えます。
実は、この登山者がこの日、私が知っている範囲のもう1名の近丸新道を登ってきた登山者。
山頂でも会うことになります。
縦走路の雪
9:01木賊山
三等三角点があり、ベンチもあります。
1月には、雪に埋もれていた木賊山の指導標も全部露出していました。
9:06木賊山発甲武信小屋に下ります。
すぐに麓から見えにくい甲武信岳の全貌が、いい感じです。
その際、滑りやすいザレ場を通過しますので、注意しましょう。
いつも風の通り道で冷たい風が吹いていました。
ザレ場に冷たい風。
厳冬期など、緊張するところです。
ザレ場を過ぎると風も落ち着き、甲武信小屋への下りでトラバース気味に下りますが、
ちょっと、嫌な雪がありますが、慎重に行けば問題ありません。
ちょっとヒヤッとしましたが、、、、。
9:17甲武信小屋
小屋に雪がありません。
当たり前ですが、屋根に雪がのった甲武信小屋の姿が焼きついています。
先ほどから見えていた登山者が休んでいました。
先に私が休憩なしで先行し、最後の登りにかかります。
2008年2月には、この最後の登りに40分以上も費やしました。
すごい登山でした。
さて、雪がなく、だいぶ楽ではありますが、そうは言っても、つらかったです。
でも、わずか15分の登りで山頂でした。
9:32甲武信岳山頂
続く。
久し振りに甲武信ケ岳、破風山、雁坂嶺、2015年5月30日
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(5)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(4)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(3)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(2)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(1)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(5)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(4)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(3)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(2)
甲武信ケ岳に登りました、2010年12月6日(1)
Posted by Y-chan at 12:35│Comments(0)
│甲武信岳
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。